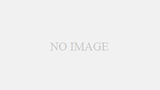公立小→公立中と進んだ長男。
最近の公立小・中では、
学力下位層は見捨てられていると
つくづく思う。
たとえば最近「おそろしく量が増えた英語の学習内容」を見ると、
つくづくそう思う。
小5から英語授業開始。
小5・小6の教科書で出てきた英単語は既習済みとして
中学英語が始まるという、騙し撃ちにあったような英語学習。
学力下位層がサポートなしでこれについていくのはかなり難しいと感じる。
学力下位層に対して補習を行う自治体は多い。
でもこの「補習」がやったふり施策なのだ。
週1回塾に通うだけでは成績は上がらないのは当たり前。
塾に行くだけではダメ。
塾から出た宿題をきちんとやり、
きちんと復習しないと成績は上がらない。
それと同じで、
週1回補習に参加しただけでは成績は上がらないのも当たり前。
長男が通う自治体でやっている補習では、
宿題が出されることはないようだ。
週1回補習に参加して終わり。
生徒が復習したかを学校側がチェックしている形跡はない。
そして、補習を担当するのは
非常勤講師やボランティアだったりする。
運良く、若くて非常に優秀な先生にあたるかもしれない。
でも通常の授業では学習内容が定着しない生徒たちの学力を上げるには、
それなりのスキルがある先生でなければ無理だろう。
正直言って、
学校側が本気で学力下位層の学力を上げようと思って
補習をやっているようには到底みえない。
「中学生になってからでは、
もう、どう頑張っても勉強なんかできるようになるわけがない。」
先生方はそう思っているはずだ。
だから保護者は仕方なく塾に子どもを通わすことになる。
結果、
割を食うのは、
保護者がその事実に気づいていない、
塾に通っていない子どもたちだ。
特別支援教育にせよ補習にせよ、
学校ですべてやろうとせず、
保護者が民間教育機関を選んでそこに任せる方法もあるだろう。
でも、そういった方法が採用される可能性はおそらく、ない。
つまり「学力下位層は学力向上を学校に期待してはいけない」。
学校の先生はすでに忙しすぎるのだ。
今以上を期待するのは不可能だ。
少なくとも勉強に関しては、
学校に対して、
「これをやってもらいたい」・「ああしてほしい」・「こうしてほしい」
とは思わないほうがいい。
つくづく、そう思う。