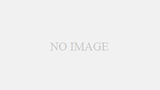現状、我が家は、公教育として特別支援教育や発達支援を受けていない。
今回はその理由を含めて、発達障害児・発達障害者への支援の現状について、今現在、私が思っていることを書く。
発達障害バブル
現在、特別支援学級も特別支援学校も増加の一途をたどっている(官邸ホームページ)。
平成16年から平成26年までの11年間で、
・特別支援学校の在籍者数は1.3倍、
・特別支援学級の在籍者数は2.1倍、
・通級指導教室の在籍者数は2.3倍、
に増えている。
生徒の総数は減少傾向であるのにも関わらず、である。
国を挙げての発達障害者支援である。
教師不足と学校統廃合
一方で、団塊ジュニア世代を教えるために40年ほど前に大量に採用した教師がここ数年大量退職する時期を迎えている。このため小学校では教師不足が深刻化している。
発達障害支援以前に、学校環境が整っていない感がある。
加えて、費用削減を目的として全国で小中学校の統廃合が進められている。
人手不足で教師が足りないうえに、費用削減のために全国の小中学校を減らそうとしているのにも関わらず、なぜ発達障害児支援だけは拡大路線を突き進むのだろうか。
監督者の指導のもと、より多くの発達障害者を非正規として安く使おうとしたのか?と勘繰ってしまう。
経験ある教師が不足している学校教育界では「分ける教育」をすすめるほうが教師にとって効率的なのか?
でも「分ける教育」を推し進めた結果、発達障害の子どもたち自身は生きる力が身につくだろうか?
その答えはまだ分からないけれども、我が家では分ける教育を選択しなくて良かったと思っている。
能力別クラス
発達障害に限らず、学力向上についても「能力的クラスにすれば学力は向上する」などと言われている。
けれども、学校を見ていると、分ければ分けるほど下位クラスに在籍する子どもたちの学力は低下していくような気がする。
東京都では小人数算数という制度を導入している。
このため、東京都では小学校の算数の授業は成績別(原則)で分けられた小人数クラスで行われている。
クラスを分けると、下位クラスの子どもたちはそのクラスの中で甘んじてしまい「勉強が得意な人たちはどうやってその問題を考えるのか」を体感しないまま成長していくのが怖い。
だから、小学校の算数の授業で下位クラスに在籍している我が家の長男には、小5から塾に通ってもらうことにした。
塾には色々な学力レベルの子どもたちが通っているから、塾は学校の授業よりも多様性がある子どもたちと一緒に勉強できるメリットを感じている。
就労支援より特技
我が家の長男(発達凸凹)はその特性ゆえに「大企業に入社して定年まで同じ会社でずっと働く」という働き方は難しいだろう。
まだ社会に出ていない長男、今のうちに自身の好きなことの中から自分の特性を生かした仕事を本人が見つけてほしいと思っている。
仕事のしやすさ心地よさを考えると、発達障害者は組織の中で歯車として動くよりも、個人の裁量が大きい仕事をしていくほうがよいのだろう。
そうなると、自ずと職人的な内容の仕事を選ぶことになるだろう。
発達障害者の就労支援のやり方をみていると「企業の中で発達障害の人を活用すること」を期待しているようだ。
発達障害者をなんとか活用することで、最近の深刻な人手不足を解消したいという意図があるのだろう。
けれども、企業の中で配慮を受けながら働くよりも特技を生かしてフリーランスかそれに近い働き方で働くほうが、発達障害を持つ本人の能力が発揮できる場が多いと感じている。
そうなると、発達支援施設や就労支援施設に通ってお仕事を紹介してもらうよりも、幅広い人たちと出会える場(大学・趣味の活動など)で色々な人たちからの知見を得るほうが、やりたい仕事・やりがいがある仕事を自分で見つけたという自信につながる。
それに、今は深刻な人手不足だからこそ、発達障害者をなんとか就労させて人手不足を解消しようという動きがある。
けれども外国人が労働力としてどんどん入ってくれば、発達障害者の支援などという面倒くさいことよりも外国人を雇ったほうが早いということになるのは明らかだ。
今は追い風が吹いている発達障害児・発達障害者支援も、これから先、景気が悪くなり、また外国人労働力が増えれば、特別支援教育や発達障害児(者)者支援なんて費用対効果が低いものはどんどん削減されるに決まっている。
だからこそ、我が家の長男には特別支援教育とか発達障害児(者)支援とかに頼らずに、好きなことを見つけて特性を生かした仕事を見つけてほしい。