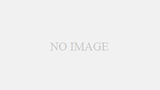2025年3月に小児科医の榊原洋一先生が亡くなられたことをだいぶ経ってから知った。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
榊原先生は昔、ある研修会の講師として講演してくださった際に一度お目にかかったことがある(以前も書いた)。
そのとき一聴衆に過ぎなかった私は榊原先生とお話する機会がなかったけれど、しばらくして長男に発達の心配が生じた後は榊原先生のブログを拝読していた。
榊原先生はインクルーシブ教育の必要性を唱えていた。
ところが今は学校現場だけでなく保護者の意識もインクルーシブ教育とは逆の方向に進んでいるように見える。
「支援級を足掛かりとした特別支援教育」ルートが確立されてしまったので、それに乗っからない保護者はかえって目立ってしまう。
今は普通学級にこだわる保護者のほうが少数派になっている。
長男が小さかった頃(10年以上前)のほうが、普通学級を望む保護者は堂々としていられた。
逆に今は「手厚い支援が受けられる」という理由で、保護者が支援級や支援学校を望むケースのほうが多い。
「とりあえず普通学級でやってみてから考える」ことを望む親御さんには昔よりもやりにくくなっているかもしれないね。
なぜなら、普通学級を希望するものなら周囲から「障害の受容ができていない」と陰口をたたかれるし、「小学校高学年から中学生くらいで勉強についていけなくなる」とか「勉強についていけず不登校・引きこもりになる」と専門家から脅されるからだ。
実際は「発達に課題がある子を普通級に入れると不登校になる」とは限らない。
普通級にうまく適応して高校卒業できる子だっている。
うちの長男がそうだ。
うちの長男は一度も不登校になったことはないし、今は高校の勉強を楽しんでいる。
インクルーシブ教育が世界の潮流なのは明らかだし、私もそうであってほしい。
けれども、多忙過ぎる教育現場はインクルーシブ教育を望んでいないし、分離教育を望む保護者も少なくない。
榊原先生がブログで言及しているように、今や話は「境界知能」まで及んでいる。
何か変だよ、日本の教育(9) 子どもの14%が境界知能? 子どもを分類しタグ付けすることはもうやめてほしい!
人口のおよそ14%の人が「境界知能」とよばれる知能域(IQ70-85)だといわれているが、境界知能を持つ人まで分離教育の対象になるのだろうか。
少し前、わたしは地元の学校関係者の話を聞く機会があったが、学校関係者も「境界知能」の問題をすでに把握していることがわかった。
世間でこれだけ境界知能・境界知能と騒がれたら、そうなってしまうのだろう。
でも、長男の経験から言うと、IQもワーキングメモリも鍛えると成長とともに伸びる。
現行の学習指導要領の学習内容はおそらく過去50年間で最多のボリュームだ。
なにせ従前の学習指導要領で決められた学習範囲は削減されずに小学校に英語やプログラミング教育が導入され、中学校の英語の学習量が増え、いわゆる探求学習が加わっているのだから。
勉強についていけない子が増えている原因は本人の特性だけでなく、学習指導要領も一因だと思う。
榊原先生はブログでこう述べている。
「子どもをカリキュラムに合わせるのではなく、カリキュラムを子どもの実態(14%がついていかれない)に合わせたらいいのではないでしょうか?」
本当にそうだと思う。
たとえば…一律に小学生から英語教育を始める必要があるのだろうか。
子どもによっては、中学生になってから英語を学び始めたほうが楽に理解できる子だっている。
国語の力がある程度ないと、英語を勉強しても身につかない。
カリキュラムにこどもを合わせるのではなく、自分でカリキュラムを選べるほうがいい。
いつ英語学習を開始するかを各人で決められるほうがいい。