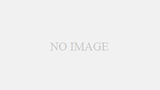小2の次男は最近になって、昨年の小1の頃の学校の様子を話してくれるようになった。
次男が小2になって、過去の出来事を振り返れるようになったのだと思う。成長したものだ。
驚いたのは、次男は、小1の頃は「音楽の授業で全然歌わなかった」ということ。
低学年(小1)ということもあり、音楽の授業は専科の先生ではなく、担任が授業をしていた。
小学校1年生の音楽の授業で「唄わない」ってどういうこと?????
次男は言った。「音楽の授業では、教室で音楽をかけながらダンスばかりしていて、歌を唄ったこと、なかったよ」と。
おそらく、次男いわく「担任の先生はピアノを弾けなくて伴奏が出来ないから歌わなかっただろう」とのこと。
今は、ピアノが弾けなくても先生になれる時代なのだ。
ダンスは立派な表現活動だし、リズムに体をのせて踊るのも立派な音楽表現だと思うので、音楽の授業でダンスするのは良いと思う。
でも小学校低学年の音楽の授業で全然歌わないのって、どうなのかしら。
歌と言語は密接な関係がある。
小さな子は声を出して歌うことで、音を言葉として認識することができる。
文字を書くことよりも先に、まず、歌うことで日本語を「音」として認識するのが大切だ。それができてこそ美しい文章が書ける。
「小学校低学年の児童にとって『言語における歌の重要性』」を理解していない担任にあたってしまったのが悲しい。
小学校低学年は文章を書くよりもまず「歌うこと」が必要だ。
親世代・祖父母世代が小学校低学年の頃は、今の子どもたちと比べると、歌う時間がずっと多かったのだよ。
思い返すと、私が小4のときの担任の先生はピアノだけでなくギターも弾けた。だから小4まで担任の先生が音楽の授業を担当していた。
当時は先生の技量が高かったのは間違いない。
今は小学校低学年から音楽専科の先生が音楽の授業を担当することが多い。業務が多すぎて音楽の授業まで手が回らない、という理由もある。
学校の音楽の授業の良いところは、みんなで声をそろえて歌えること、そして、歌うのが嫌いな子は歌っていなくてもバレないことだ。
学校の音楽の授業では、歌が嫌いな子には歌うことを無理強いせず、歌いたい子が大声で思いっきり歌えれば十分だ。
「授業で歌うこと」なんてタダで出来ることなんだから、こどもたちに「歌」をもっと経験させてほしい。