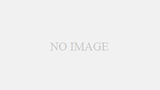日本の特別支援教育が「分離教育」にあたるとして、国連が分離教育の中止を勧告したという報道があった。
一方、この国連による勧告を受けて永岡文部科学大臣は会見で「現行の特別支援教育の中止は考えていない」と発言している。
国連の勧告について世の保護者がどのように受け取ったのか、ヤフコメ欄の保護者のコメントをずっと読んでいた。
コメント欄に書かれた保護者の意見の多くは「特別支援教育を残してほしい」という声だった。
特別支援教育を支持する声が大きいのは、この15年ほどの間に「特別支援教育が学校教育に深く浸透した」ことを意味しているのだろう。
今は小学校入学時に手厚い指導を希望して、支援級在籍を希望する保護者も少なくない。
約10年前に長男が小学校に入学するときは、特別支援教育がどんなものなのか当時は得体が知れなかったこともあり、長男の進路としては普通学級しか考えられなかったことを思うと隔世の感がある。
確かに、設備と人材が揃った特別支援学校でなければ対応が難しいケースが多々あるし、特別支援学級にしか居場所がない子どもが多くいるのもよく分かる。
だから特別支援学級や特別支援学校は存続したほうが良いと思う。
国連の勧告を受けて特別支援学級や特別支援学校をすべて失くすことは到底考えられない。
ただ、軽度やグレーゾーン(どちらもあまり使いたくない言葉だ)の場合、今もなお、通常級から支援級へと転籍するよう勧められるケースが後を絶たないのも確かだ。
通常級を現状の1クラス35名から1クラス15名程度にすれば、敢えて支援級を作る必要はなくなるし、通常級に在籍する多くの生徒にとって学びやすいと思うのだが、予算の関係なのか、「1クラスの人数を減らす」という方向にはなぜか進まない。
しっかりと目をかけてあげたほうがいいのは支援級の子どもたちだけじゃない。通常級の子どもたちだって、少人数学級でしっかりと目をかけてあげたほうがいいと思う。
支援級在籍の場合、週の半分以上を支援級で過ごさなければならない
そして、今回の報道ではじめて知ったのは、文部科学省が「支援級在籍の生徒は週の半分以上を支援級で過ごさなければならない」という通知を最近出していた、ということだ。
特定の科目だけが苦手な子どもだっているだろうに、なぜ支援級に押し込めたいのだろうか。