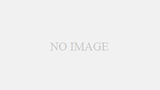次男を公立小学校に通わせていて思うこと。
こどもの勉強に対する保護者の考え方が、完全に二極化しているのよね。
長男が小学校に入学した2010年代より、10年経った今(2020年代)のほうが、保護者の二極化が激しくなっている。
公立小の保護者は、勉強が大事だと思っている親と、勉強はあまり大事だと思っていない親にきっぱりと分かれる。
勉強はあまり大事だと思っていない親は、教育に関心がないわけではない。なぜなら、習い事や部活のサポートには熱心だったりするから。
でも、こどもの「勉強」にはあまり興味がないらしい。習い事のサッカーや野球の帰り、こどもを自転車の後ろに載せながらこどもにスマホゲームをやらせっぱなしの親をよく見かける。
基礎学力をつける必要性を感じない親は「宿題を減らせ」と学校に要求する。
基礎学力をつける大切さを理解している親は「宿題をきちんと出してください」と学校に要求する。
両者は、話がまるでかみ合わない。
日本が着々と格差社会へと向かっていると感じる。
わたしは、学校の宿題くらい、きちんとやったほうがいいと思っている(宿題の量が多すぎる場合は別だ)。
こどもに基礎学力をきちんとつけさせたい親は、教育に関心がない保護者に嫌気が指して、中学受験する、というのも少なからずあるだろう。
中学受験を経て、晴れて中高一貫校に入学してみると「きちんとした保護者ばかりで嬉しい」という話、よく聞くもんなあ。
その気持ち、分かる気がする。
長男が公立中学に入学したときに感じたのだ。公立小の保護者と比べて公立中の保護者は何というか、ほわーんとしていて、ゆるい感じなのだ(以前も書いた)。
公立中学には、中受して中高一貫校に進学した層が抜けて入学してくるからね。教育熱心な家庭が抜けたせいなんだろう。
だから次男を公立中に積極的に通わせたいわけじゃない。
次男を中学受験させたくないと思っているのは、熾烈な中学受験の競争に次男を巻き込ませたくないから。
仕方なく次男を公立中学に通わせる、というのが本音だ。